あんこを作るとなると「手間がかかりそう…」と思い、作る前から諦めてしまっていませんか?
しかし、意外と簡単に作れちゃうのが、手作りあんこの魅力。
あんこを手作りできれば、好みの甘さに加減できたり、思う存分食べられる量を作ったりすることも可能です。
今回は、あんこを手作りしたことのない方でもOK!失敗なし&簡単にできる「粒あんこの作り方」を紹介します!
手づくりあんこで失敗しないポイント

まずは、あんこを手作りするうえでおさえておきたいポイントをご紹介します!失敗しないためには、これから紹介する4つのことは、怠らずに行ってくださいね♪
小豆は水につけてから煮る
小豆は「12時間から24時間程度」水につけてから煮るようにしましょう!
しかし、「小豆を水につけなくても良い」としている人が多くいるのも確かです。というのも、小豆の特質上、水につけても十分な吸水効果が得られないと言われているから。
そこで、私も小豆を水につけず作ったことがありますが…、いつもと同じ時間、火にかけても小豆の芯が残り、仕上がりも理想とは少し違っていました。(要は火が通りにくいと感じた)
そのため、失敗なく簡単に作りたい!と思っているのであれば、必ず水につけてから煮ることをおすすめします!
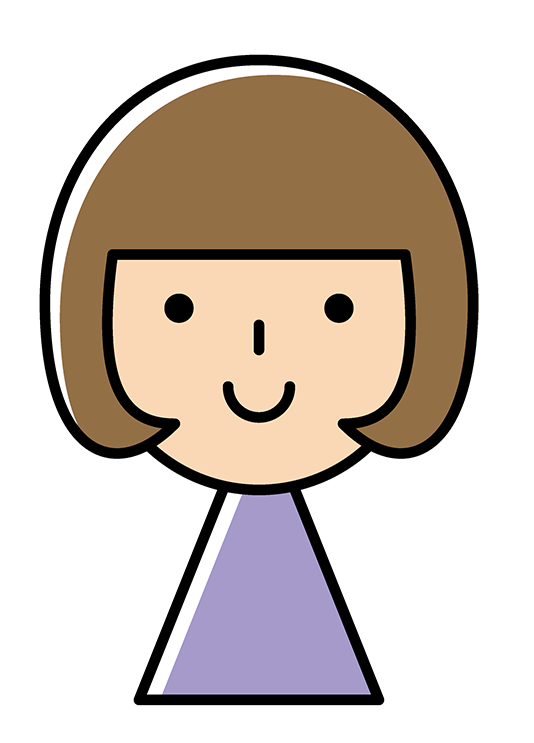
数時間の浸水は意味ないかもしれないけど、12時間以上水につければ、小豆は水を吸収し、ぷっくり膨れるよ♪そして、やっぱり火も通りやすくなる!
茹でこぼし(あく抜き)は絶対に行う
あんこを作る際には、小豆を水から茹でて、茹でこぼす作業、いわゆる「あく抜き」は必須です。
茹でこぼしをしないで、そのまま火を通して砂糖を加えた場合、小豆の渋みや苦みが残ってしまいます。少し面倒な作業ではありますが、美味しいあんこを完成させるためには絶対に怠らないでくださいね♪
砂糖を入れるのは小豆が柔らかくなってから
砂糖入れるタイミングは、小豆が柔らかく煮えてからです。
小豆が煮える前に砂糖を入れてしまうと、それ以降小豆が柔らかくなることはないので注意してくださいね!
砂糖の分量は目安として把握する
砂糖の量は好みですが、目安は把握しておきましょう。
砂糖の分量は、小豆と同量又は、小豆に対して8割程度の分量を入れるのが基本です。
ちなみに、いくら甘さを抑えたい!と思っても、小豆の半量まで減らすのはNG。
なぜなら、砂糖が少ないとパサパサとした食感になり、あんの質感が悪くなるからです。また、砂糖が少なすぎると「腐りやすい」というデメリットも…。
関連記事:【あんこの賞味期限】日持ちはどのくらい?腐るとどうなる?保存方法も解説!
具体的な目安としては、以下のとおりです。
- 砂糖は甘さ控えめ:小豆よりやや少ない量(例、小豆500gに対して砂糖400g)
- 甘みをしっかりつけたい:小豆と同量か、それ以上加える
初めてでも大丈夫!粒あんこの簡単な作り方
それでは、粒あんこ作りをしたことがない人でもOK!いつも私が作っているレシピをご紹介します!
砂糖を加えるまでは、長い時間あんこに付きっきりでいる必要がないので、手軽に簡単に作れちゃいますよ♪
材料
- 小豆:500g
- 砂糖:400~500g(好みで)
- 塩:ひとつまみ
- 水:適量
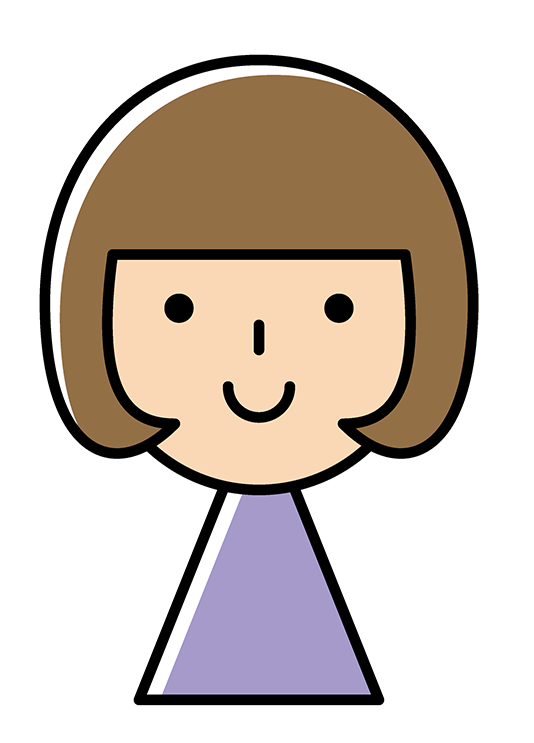
あんこの材料は、小豆と砂糖がメイン。他に、難しい材料をそろえる必要がないので、意外と手軽に作れるのです!
作り方
では、あんこの作り方を以下6ステップにわけてご紹介します。
ステップ1.小豆を洗い、水につける
大きめのボールに小豆を入れて、キレイに洗いましょう!
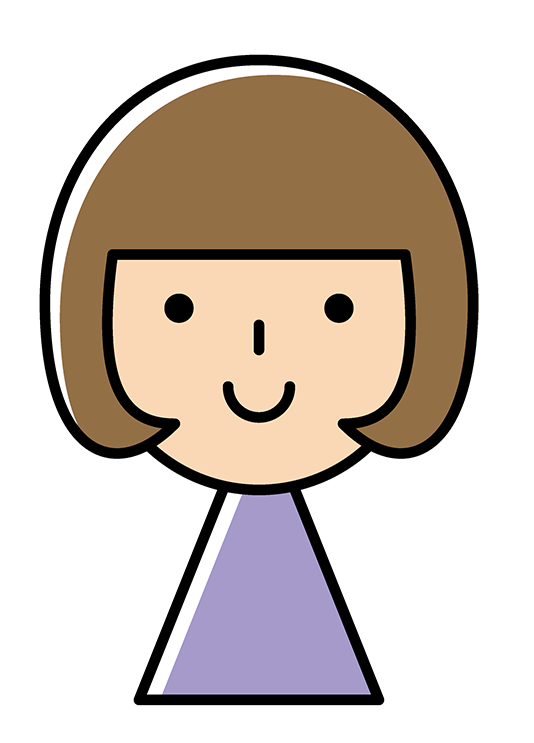
細かいゴミや小豆の破片などが入っていることが多いので、しっかり洗いましょうね。
洗った小豆とたっぷりの水を同じボールに入れて、12時間から24時間浸します。
ちなみに、小豆が水を吸収したという目安は、水が見えなくなるくらい小豆が膨れ上がったときです!
ステップ2.沸騰~茹でこぼし
よく膨れた小豆を、大き目の鍋に入れ煮ます。
水の量は、小豆を入れた状態で水嵩4㎝くらいまで。かなりたっぷりの水です。
それを中火にかけ、沸騰させ茹でこぼしをします。
具体的には、ぐつぐつと1分くらい沸騰させてから、ザルに上げて水を切り、また小豆を鍋に戻しましょう。
ステップ3.再び水を入れ沸騰
そして、再び水を注いで中火にかける。
このときの水の量は、小豆を入れた状態で水嵩2㎝くらいに。
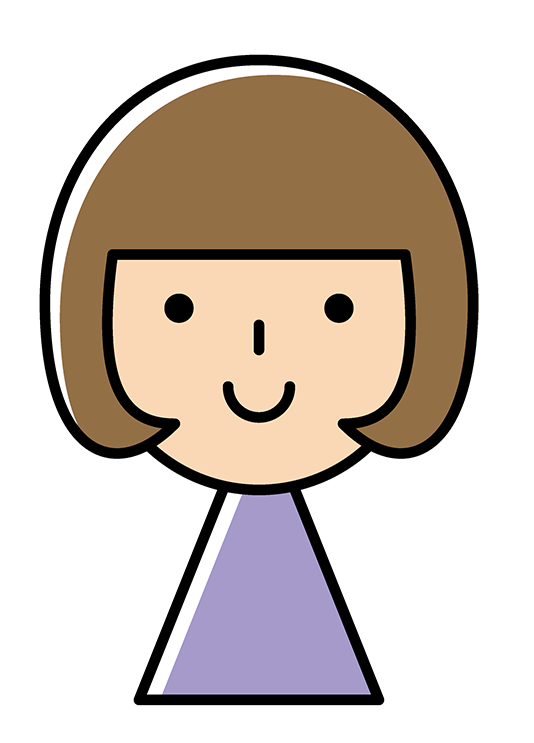
この時点で、あまりにも水を多くしてしまうと、水分を飛ばす際に時間がかかってしまうからです!
沸騰後は弱火にし、蓋をした状態で10分くらい火にかけ、火を止めて、そのまま蒸らしましょう。
ステップ4.冷めたら再度火を入れ蒸らす
手で触れるくらい鍋が冷えたら(約2時間くらい)、その状態で再度中火にかけます。
また、沸騰したところで弱火で10分かけ、その後、火をとめまた蒸らします。この間、蓋は絶対にあけないようにしましょう。
蒸らし、また鍋が人肌程度になれば(約2時間くらい)、蓋を空け小豆の状態を確認。
皮が割れ、指で潰せるくらいの柔らかさであればOK!もし、まだ固いようであれば、少し水を足しステップ4を再度行いましょう。
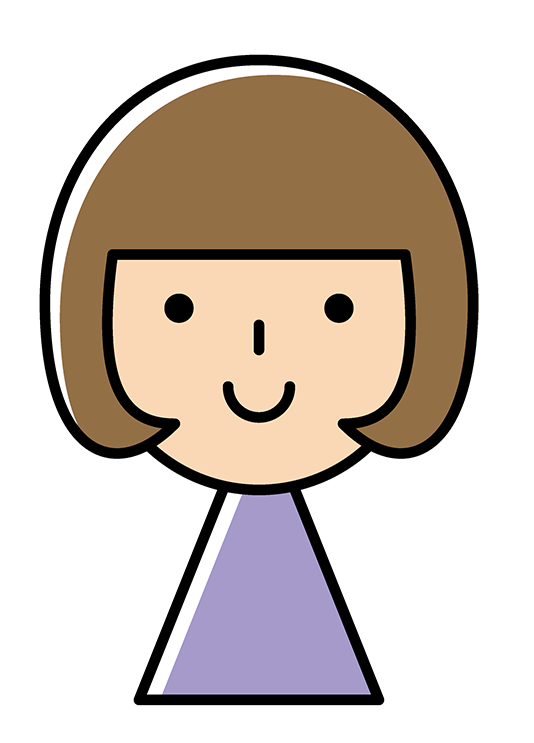
ここまで、小豆を蒸らしている間は火を止めているわけだから、他の家事や好きなことをして時間を過ごしてOK!
ステップ5.砂糖を加える
小豆が充分柔らかくなっているのを確認できれば、砂糖を入れます。
弱火から中火の間の火加減で、焦げないように練りましょう。
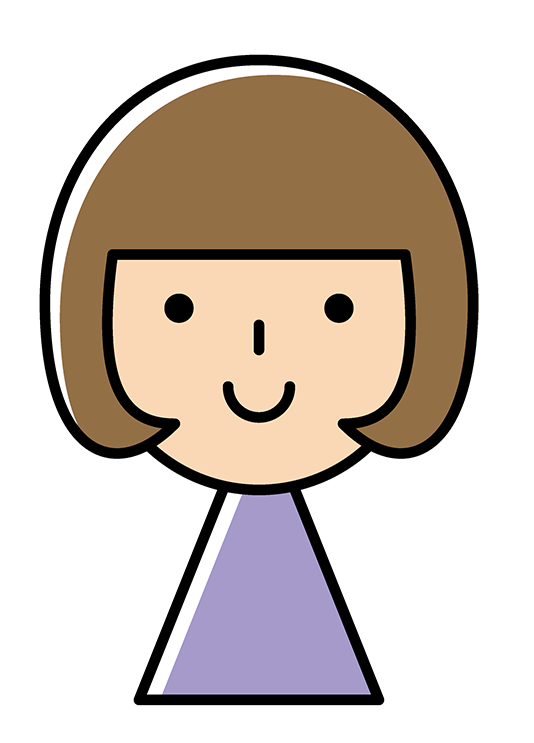
とくに、なべ底は焦げやすいので注意してくださいね!
だんだん水分が飛んできて、少しもったりとした状態になってきたら、塩をひとつまみいれてください。
正直、塩入れるタイミングは「砂糖入れた後」であれば、いつでもOKです。
ステップ6.水分が飛ぶまで練る
なべ底に「の」字が書けるくらいまで、練り合わせます。
分量にもよりますが、おおよそ30分から1時間くらいで、程よいかたさになるでしょう。
ちなみに、あんこの用途にもよりますが、おはぎであれば「の」字が書けるくらいの硬さ。
あんぱんの中身に使うなど、固めのあんこが良いのであれば、それよりもう少し固めにしたほうがよいでしょう。
これで、あんこの完成です!
まとめ
「あんこは、熟練の技をもったおばあちゃんしか作れない!」と思っている方もいるかもしれませんが、実際のところ、そんなことはありませんよ!
ポイントさえおさえれば、手間をかけずとも自分好みの美味しい粒あんを作ることができます♪
ぜひ、チャレンジしてみてくださいね!



コメント