あんこが大好きなママやパパなら、可愛いわが子にも「あんこを食べさせたいな~」と思うのではないでしょうか。
私も現在5歳の息子がいますが、しっかりと親の血を引き継ぎ「チョコレートは嫌いだけど、あんこならたくさん食べたい!」と、大のあんこ好きに…。
とはいえ、息子にあんこを食べさせ始めるタイミングは迷ったものです。
そこで今回は、あんこは何歳から食べさせてもOK?目安の年齢&子どもにあんこを食べさせるときのポイントについてお話します♪
あんこは何歳から食べさせていい?

あんこは柔らかーく煮てあるから、赤ちゃんでも食べさせても良い気がしますが、実際のところどうなのでしょうか?
実は、0~2歳の乳児期には向きません。ここでは、具体的な理由についてお話しますね。
砂糖の多いあんこは3歳を過ぎてから
砂糖がたくさん含まれている、あんこ又はあんこのお菓子は「3歳を過ぎてから食べさせる」ことを推奨している育児書が多くあります。
理由としては、3歳ごろまでの子どもの味覚は安定していない状態で、あんこに拘わらず砂糖がたくさん入った食べ物を食べると、甘味が強いお菓子しか好まない子どもに。それによって、虫歯ができやすいことが懸念されるからです。
なかには、洋菓子に使われるような生クリームやチョコレートよりは、あんこのお菓子の方がマシなのでは?と考える人もいるかもしれませんが、あんこは想像以上に砂糖を多く含んでいる食べ物です。
ですから、砂糖が入ったあんこであれば3歳を過ぎてから与えるのが無難といえるでしょう。
とはいえ、3歳になったからといって、急にたくさん食べさせていいわけではありませんよ!あんこはあくまでも嗜好品のため、与える量は少しだけにしましょうね!
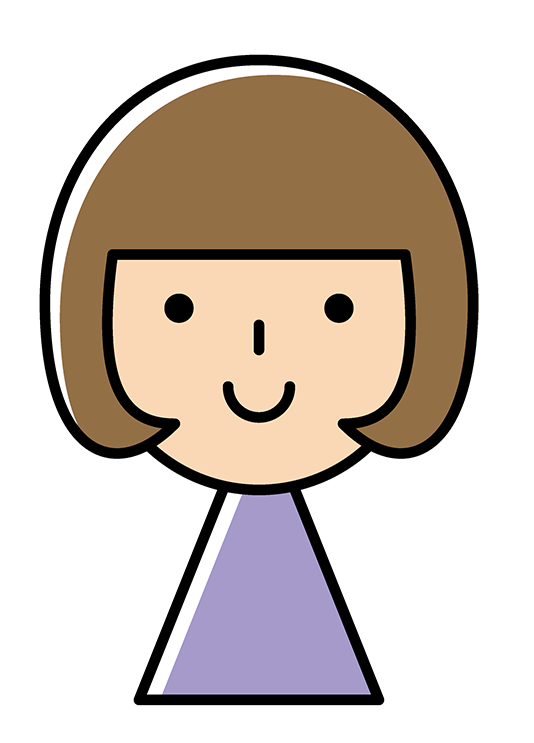
我が家も、甘さ控えめの手づくりあんこを3歳から食べさせていました。
関連記事:手間をかけたくない人必見!手作り粒あんこの簡単レシピ
「無糖あんこ」であれば生後7~8か月からでもOK
あんこの原料である「小豆」は、健康効果に期待できる食材でもあります。
前項では、砂糖が入ったあんこは3歳までNGとお伝えしましたが、砂糖不使用のあんこであれば離乳食として、7~8か月の赤ちゃんでも食べてOK。
ただし、小さな赤ちゃんに与える際は、アレルギー反応に注意が必要です!赤ちゃんの体調が良いとき・少ない量から与えるようにしましょうね。
ちなみに粒あんは、赤ちゃんにとって「皮が飲み込みずらい+消化されにくい」ので、取り除くことも忘れずに…。
あんこを食べさせる時のポイント

あんこを食べさせて良いとする目安の年齢がわかったところで、子どもあんこを食べさせるときのポイントもチェックしましょう!
少量ずつ食べさせる
あんこを与えられる年齢に達したら、まずは少量からスタート。
無糖・加糖かかわらず、食物繊維が豊富なあんこは消化機能が未発達な赤ちゃんには、負担が大きい食べ物だからです。
また前述の通り、甘いあんこは一度にたくさん与えてしまうと、その甘さを覚えてしまい、さらに欲するケースが多々あります。あんこは、何かのご褒美として食べさせるのが良いかもしれませんね!
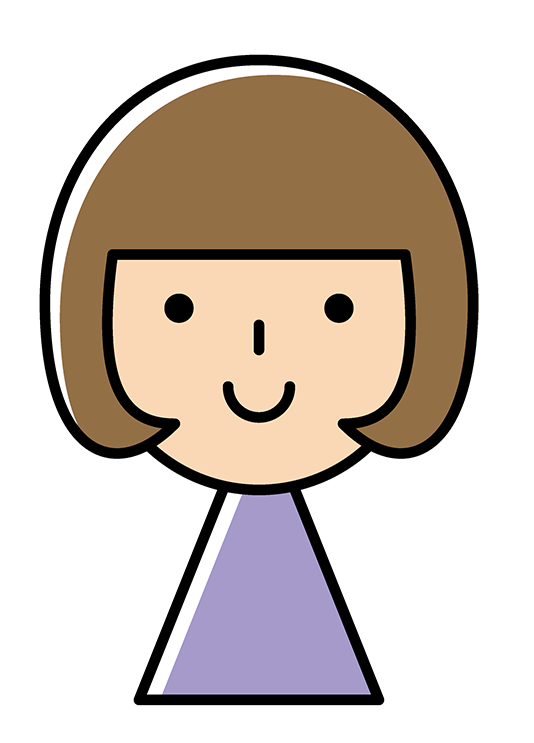
具体的には、どら焼きやアンパンなどあんこのを使った食べ物の場合は、中身のあんこの量を半分以下にするなど、少量ずつにしましょう!
頻繫に食べさせない
1回に食べさせる量を少量にすることも大切ですが、頻繫に与えないこともポイントです。
少ない量であっても毎日与えてしまうと、それもそれで甘さへの欲求が激しくなってしまう&虫歯にもなりやすくなるため、月に数回程度にしましょう。
アレルギーにも配慮する
あんこの原料である「小豆」は、食物アレルギーの可能性は他の豆類ほど高くはありません。
しかし、「可能性が全くない」ということはありませんので、ほかのアレルギーリスクのある食品と同様に、初めて食べさせる際は、少量ずつ様子を見ながらにしましょう。
甘さ控えめのものを選ぶ
あんこを子供に食べさせる場合に問題となるのは、あんこが甘すぎるからです。たっぷりの糖分は、子どもの虫歯や肥満、糖尿病の危険もあり得るので、甘さ控えめのものを選びましょう。
理想としては、砂糖の量を好みに調節できる「手づくりあんこ」がおすすめ。とはいえ、なかなか作るのは大変なのも事実。
市販のものを与える場合は「甘さ控えめ」、もしくは後述する「無糖のあんこ」を選らんで食べさせてあげてくださいね。
消化不良が心配であれば「こしあん」をチョイス
小豆の皮には食物繊維が多く含まれますが、消化されにくいという特徴があります。
3歳を過ぎればほとんどの場合、小豆の皮程度であれば消化できるはずですが、なかには消化不良が懸念されるお子さんもいるでしょう。
その場合は「つぶあん」よりも「こしあん」をチョイス。手づくりする場合には、前もって薄皮を取り除く、もしくは裏漉ししてくださいね。
市販商品でも「無糖あんこ」をチョイス

前述の通り、あんこの原料である「小豆」は健康によいはずなのに、3歳以上から推奨されることが多い食品です。その理由が、砂糖がたくさん入っているから。
ですから、砂糖が入っていない「無糖のあんこ」であれば安心なわけです。
そこでおすすめなのが以下の商品です。
まとめ
あんこを与える目安の年齢としては、味覚が安定してくる3歳以降がおすすめ。
しかし、砂糖を一切加えずに小豆を煮ただけの「水煮」であれば、7~8か月の赤ちゃんでも食べて大丈夫です。ただし、アレルギー反応に注意しながら。
あんこは、生クリームやチョコレートに比べると「体に悪くなさそう」と思われがちですが、しっかりと砂糖が入っているので、お子さん用のあんこのお菓子を選ぶ際は「甘さ控えめ」をチョイスしましょうね♪



コメント